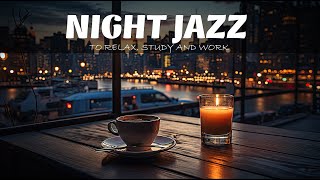18世紀日本絵画史から考える蔦重・歌麿・写楽【ゲスト:佐藤康宏(美術史家/東京大学名誉教授)】
Автор: 春木で呉座います。
Загружено: Прямой эфир состоялся 26 апр. 2025 г.
Просмотров: 1 743 просмотра
蔦屋重三郎に見出されて世に出た喜多川歌麿や東洲斎写楽は、
市井の看板娘や歌舞伎役者の姿を「大首絵」という形式で、
上半身をクローズ・アップして描き、一世を風靡した。
江戸の人々を、そして今日のわたしたちをも惹きつける浮世絵は、いかにして誕生したのかーー
佐藤康宏『若冲の世紀ー十八世紀絵画史研究ー』(2022年、東京大学出版会)は、
日本美術史上最も創造的な時代のひとつといえるこの時期の京都・大坂・江戸の絵画と版画を論じた、
40年に及ぶ著述の集大成である。
複製技術の普及を背景に、
若冲、蕭白、応挙といった画家が次々登場し、
異なる個性を発揮していったこの時代を論じる本書の終章は、
「大首絵というモードー歌麿と寫楽」と題されている。
言葉が紡ぐ「物語性」や「意味」から解き放され、
形象の力で現実を捉えようとしたことが、
二者の「大首絵」の革新であり、
新しい時代の、新しい絵画の在り方の提示であった。
東京大学出版会のPR誌『UP』に13年に渡り連載された「日本美術史不案内」では、
江戸時代の美術に限らず、このチャンネルではたびたび話題になる洛中洛外図屏風や伝頼朝像ほか、
縄文時代の土器から現代のマンガや映画、小説まで、
古今東西の造形や芸術・文化を鋭く論じ、
この4月にその150回の連載をまとめた書籍を刊行された。
https://www.utp.or.jp/book/b10124146....
18世紀絵画史を締めくくる、歌麿・寫楽の「大首絵」の意義、
さらには『日本美術史不案内』に案内いただき、
佐藤康宏先生の美術史研究の足跡に迫るーー
******************
ゲスト紹介(東京大学出版会ウェブサイトより)
佐藤 康宏
1955年 宮崎県生れ. 東京大学文学部美術史学専修課程卒業。同大学院人文科学研究科修士課程修了。東京国立博物館学芸部、文化庁文化財保護部、東京大学大学院人文社会系研究科・文学部教授を経て、現在東京大学名誉教授。
<主要著書>
『若冲・蕭白』(小学館、本論「蕭白新論」が第4回國華賞受賞)、『湯女図―視線のドラマ』(平凡社、第6回倫雅美術奨励賞受賞、ちくま学芸文庫)、『浦上玉堂』(新潮社)、『講座 日本美術史』全6巻(共編、東京大学出版会)、『改訂版 日本美術史』(放送大学教育振興会)、『絵は語り始めるだろうか―日本美術史を創る』(羽鳥書店)、『若冲伝』(河出書房新社、第70回芸術選奨文部科学大臣賞受賞)、『若冲の世紀― 十八世紀日本絵画史研究』(東京大学出版会、第21回德川賞受賞)ほか。

Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке: