野菜の土作りの基本(ふかふかの野菜が良く育つ土作りができる!)初心者でも土作りの基礎が簡単に身に付く!
Автор: 野菜作りの教科書 Vegetable Beginners Guide
Загружено: 11 февр. 2025 г.
Просмотров: 65 642 просмотра
良い土がよい野菜を育てると言われるように、立派な野菜を作るうえで土作りは大事な作業です。
家庭菜園をしている人の多くが実感しているのが、土作りの大切さではないでしょうか。
初めたての頃は土なら何でもよいと軽視してしまいがちですが、そんなことはありません。土作りの成功は野菜作りの成功と考えても良いくらいです
野菜作りは作を肥やさず土を肥やせが基本で、単に肥料を混ぜただけでは良い土とは言えません。
作物が良く育つ土作りは一体どのようにすれば良いのでしょうか。
今回の動画では、土作りをする目的や野菜がよく育つ土壌環境、土壌微生物と堆肥の関係など、土作りの基本を丁寧に解説していきます。
土作りは基本を少し理解しているだけで結果が大きく変わります。土作りの基本を覚えて立派な野菜を育てましょう!
【関連動画】
春の土作り
• 夏野菜の土作り(春の畑作りの基本と夏野菜向けの土作りのやり方)驚くほどよく...
夏・秋の土作り
• 秋野菜の土作り(夏の土作りで秋野菜の収穫量が劇的にアップする!)夏の畑作り...
冬の土作り
• 土作りの裏技(冬の土作りで春夏野菜の収穫量が劇的にアップする!カチカチ用土...
ぼかし肥の作り方
• ぼかし肥の作り方(肥料代を大幅に節約できる!メリットや正しい使い方を詳しく...
米ぬかの効果と使い方
• 米ぬかの効果と使い方
籾殻の効果と使い方
• もみ殻の効果と使い方
【公式サイト】
野菜の津土作りの基本
https://kateisaiennkotu.com/kihon/tut...
動画作成の励みになります。もしよろしかったら、「チャンネル登録」と「👍」をお願いします!
https://onl.bz/qfJXtsv
【目次】
0:00 オープニング
0:14 野菜の土作りの基本
1:19 土作りをする目的
2:36 野菜がよく育つ土壌環境とは?
12:54 野菜の土作りの基本まとめ
土作りをする目的
土作りが野菜栽培で重要というのは多くの方が知っていると思いますが
具体的にどのような目的で行うのかと聞かれたら、はっきり答えられるでしょうか
自然界で作られる土壌では、雑草や土の中にいる小動物、微生物などの働きによって
土が柔らかくなり、保水性と通気性が高まり、土壌pHが適正になり、植物に必要な養分が供給されています
また、自然界では植物は役目を終えて枯れると土に返り、微生物によって分解され次世代の肥料となります
これは土壌微生物の活性が高い環境になっているからです
一方、菜園やコンテナといった閉鎖された空間では、自然界ほどの土壌の再生が行われないので
連続して作物を育てると、次第に作物の成長が悪くなって、病害も出やすくなり、収量も減ってしまいます
そこで、人為的に土壌の改善や生育不良になるさまざまな要因を取り除き、豊かな環境を作ってやる必要があります
つまり、自然界と同じ土壌環境を人為的に作ってやることが土作りの目的です
野菜がよく育つ土壌環境とは?
野菜がよく育つ土壌環境とは、一体どのような状態のことでしょうか
野菜作りは土作り次第で、成功するか失敗するかが決まるといっても過言ではなく
野菜が嫌う土壌では作物はうまく育ちません
野菜がよく育つ土壌環境を作るために大事なポイントには、どのようなものがあるのか見ていきましょう
1.柔らかい土壌
野菜は根を土中に広く深く張らすことが重要になります
これは野菜は根から養分や水分を吸収することで、地上部の茎葉や果実が大きくなるからです
野菜の根は想像している以上に広く、深くまで伸びます
トマトやナス、スイカなどは深さ1メートル以上、 半径2メートル以上まで根が伸び、白菜やキャベツ、ホウレンソウなどの葉野菜でも、深さ1メートル以上も根を張ると言われています
根が力強く張った野菜は、収穫量が増えて病害の発生も抑制することができます
粘質土壌や極度に乾燥している土壌では、植物は根をじゅうぶんに張ることができません
丁寧に耕うんして、堆肥などの有機物を投入し、柔らかな土作りを目指しましょう
堆肥とは、藁、枯れ草や枯れ葉、藻類などの植物や、鶏ふんや牛ふんといった家畜のふんを堆積して発酵させたものです
耕うんは土を砕いて柔らかくする作業のことで、作物の種まきや苗の植え付けの準備として行います
耕うんの目的は、土を砕いて根を張りやすくすること以外に、深く耕して土中に大きなすき間を作るといった目的もあります
不耕起でも前作野菜の根の跡などすき間はありますが、小さなすき間ばかりになってしまいます
空気を含む大きなすき間部分を気相、水を含む小さなすき間部分を液相、土粒という土の本体部分を固相と言い、これらの3つを併せて土の三相と言います
野菜が良く育つ土壌にするには、大小さまざまな隙間を作ることがポイントで、野菜作りに適した土壌は、固相が40~50%、気相が25~30%、液相が25~30%が理想的なバランスです
土の表面しか耕していない土壌では、長年の雨と乾燥の繰り返しによって、下層の土の粒度が密になって排水性が悪くなっていきます
表面の用土と下層の用土を入れ替える天地返しもおすすめです
2.保水性と通気性のよい土壌
野菜がよく育つ土壌は、保水性と通気性の相反する性質を併せ持った環境です
有機物がない用土はただの鉱物で、保水性がなくなってしまいます
作物は根から水に溶けた肥料を吸うので、保水性のない土壌だと、作物が養分をうまく吸収できなくなって生育が悪くなってしまいます
また、畑の土が粘土化しすぎても、団粒構造が少なくなって通気性が悪くなります。
作物の生長には多くの酸素が必要です
粘土化した土壌は、水はけが悪くなって根が呼吸できなくなり、その結果、地上部の生育も悪くなり、根腐れを起こしやすくなります
自然界では落葉や小石などが土に混ざることで、保水性と通気性のよい土壌が形成されていきますが、栽培を繰り返す家庭菜園では、人為的に手を加えて保水性と通気性の良い土壌を作ることがポイントです
保水性と通気性を良くするために、堆肥などの有機物を継続的に投入してやりましょう。
3.障害物が少ない土壌
小石や土塊、前作の茎や根などの異物が少なく、土がフカフカと柔らかいことも大切です
異物が多いと野菜は十分に根を張ることができず、貧弱な野菜になったり、根野菜などは食用部がいびつな形になったりします
土作りの際に、まずは用土をスコップで掘り起こしながら、小石や前作の茎や根などを取り除き
大きな土塊を手で砕きながら、鍬などを使って20~30cmの深さまで用土をひっくり返すように耕します
風化した上層部の土を下層部へ、下層部の土を上層部へと入れ替えて、空気に触れさせてやりましょう
土壌中の酸素が増えると、植物の根の酸欠を防ぐことができ、土中の微生物の働きも活発になります。
4.適正なpHを保った土壌
日本で栽培されている野菜の多くは、弱酸性から中性の土壌が適しています
pH5.5~6の弱酸性を好むのは、ダイコン、ジャガイモ、サトイモ、パセリなどで、カボチャ、キュウリ、トマト、ナス、キャベツ、レタス、ニンジンなどは、pH6~6.5を好み、ほうれん草、タマネギ、ゴボウ、アスパラガス、テーブルビートなどは、pH7の中性に近い土壌を好みます
このように野菜ごとに生育に適したpHが違っているので、野菜を植え付ける前に酸度チェックを行って、適正な酸度調整を行っておきましょう
同じ場所で何度も繰り返し野菜を育てていると、用土が自然に酸性へと偏っていきますが、これは作物が養分として土壌中のカルシウムを吸収する以外に、日本の土壌の多くが酸性が強い火山性の母岩からできていることや
雨水の中に炭酸が入っているため、土壌中のカルシウム、マグネシウム、カリウムが追い出され、土壌に炭酸が吸着されてしまうからです
用土が酸性になると作物はホウ素やモリブデンの欠乏症が発生しやすくなります
さらにマンガン、鉄、銅、亜鉛は酸性で溶けやすい性質をしているので過剰に吸収され、生理障害も発生しやすくなります
土壌酸度は市販のpH測定器やリトマス試験紙(測定液)で簡単に調べることができます
ペーハーメーター(ペーハーチェッカー)というアイテムなら、土に挿すだけで簡単に測定できるのでおすすめです
デジタル表示の測定器なら、小数点以下の細かな数字も拾えるのでより正確です
土壌が酸性に傾いているときは、苦土石灰や炭酸カルシウムなどの土壌改良材を投入して、人為的にpHを適正値に戻してやりましょう
ただし、やみくもに投入すると、逆にアルカリ性に偏ってしまうので注意しましょう
用土が強アルカリ性になると、野菜が微量要素を吸収することが出来なくなり、生育が悪くなってしまいます
アルカリ性に偏ってしまった時は、ホウレンソウやビーツ、トウモロコシ、アスパラガスなどアルカリ性の土壌に強い作物を植えて石灰分を吸収させるか、酸度未調整のピートモスを土壌にすき込んで中和させましょう
苦土石灰で酸度調整するときは、pHを1.0上げるには石灰を1㎡あたり400g(60cmのプランターで約50g)が目安です
また、植え付けの直前に石灰を入れると根を傷めてしまうので、最低でも約2週間前には酸度調整を完了させておきましょう
5.土壌微生物の住む土壌
肥沃な用土は土粒や水・空気以外にも、さまざまな有機物と、有機物を分解する土壌微生物の存在が不可欠です
土壌微生物の代表は、細菌(バクテリア)・菌糸菌(カビ)・放線菌(菌糸を伸ばす細菌)、小動物(ミミズ・ヤスデ・トビムシ・ダニ類・センチュウなど)です
微生物の種類と量を増やすことで、土壌中の有機物の分解速度が早まり、吸肥効果が高まることが分かっています
また、土壌微生物は用土の粘着性を高める働きもします
粘着性が低いと、用土から肥料が流れ出やすくなり、保肥性が悪くなります
土壌微生物が有機物を分解する際に粘性物質を分泌して、土の粒子が団子状になった団粒構造の用土ができ上がります。
団粒構造になっている土壌は、保水力・排水性・通気性に優れています
団粒構造の用土には、土壌微生物が多く存在しています。
微生物の数を増やし、活動を促進するために、微生物の餌となる堆肥を入れてやりましょう。
土壌微生物が住みやすい環境を作ることで、作物が育ちやすい土壌を作ることができます。
6.養分を供給した土壌
自然界では、落葉や生物の死骸などの有機物が微生物によって分解されて、新たな植物の養分となり命を繋いでいます。
連作を繰り返すコンテナ栽培や露地栽培では休耕期間が短いため、自然の循環サイクルが機能しない環境になっています
新たな養分を作る期間がない環境下では、植物に必要な養分が絶対的に不足してしまいます。
養分が不足すると植物は生育が悪くなったり、病害に弱くなったりします
人為的に養分を補うことで、野菜を大きく健常に育てることができます
野菜作りに欠かせない基本の養分は、チッソ、リン酸、カリウムで、これらは肥料の三大要素と呼ばれています。
このほかにも、カルシウムとマグネシウム、微量要素としてイオウや鉄、マンガン、亜鉛などの微量要素も必要です。
栽培前に化成肥料やぼかし肥などを施しておきましょう。
ただし、化成肥料は微生物のエサにはなりません。
堆肥などの有機質を入れないと粘着物質が生成されず、土が単粒化構造になってサラサラの状態になってしまいます。
単粒化構造の土壌は、密度が高く、空気や水の層が非常に少なく、植物にとっては生育しにくい状態です。
化成肥料だけに頼るのではなく、有機質資材も使いながら土壌に養分を供給してやりましょう。
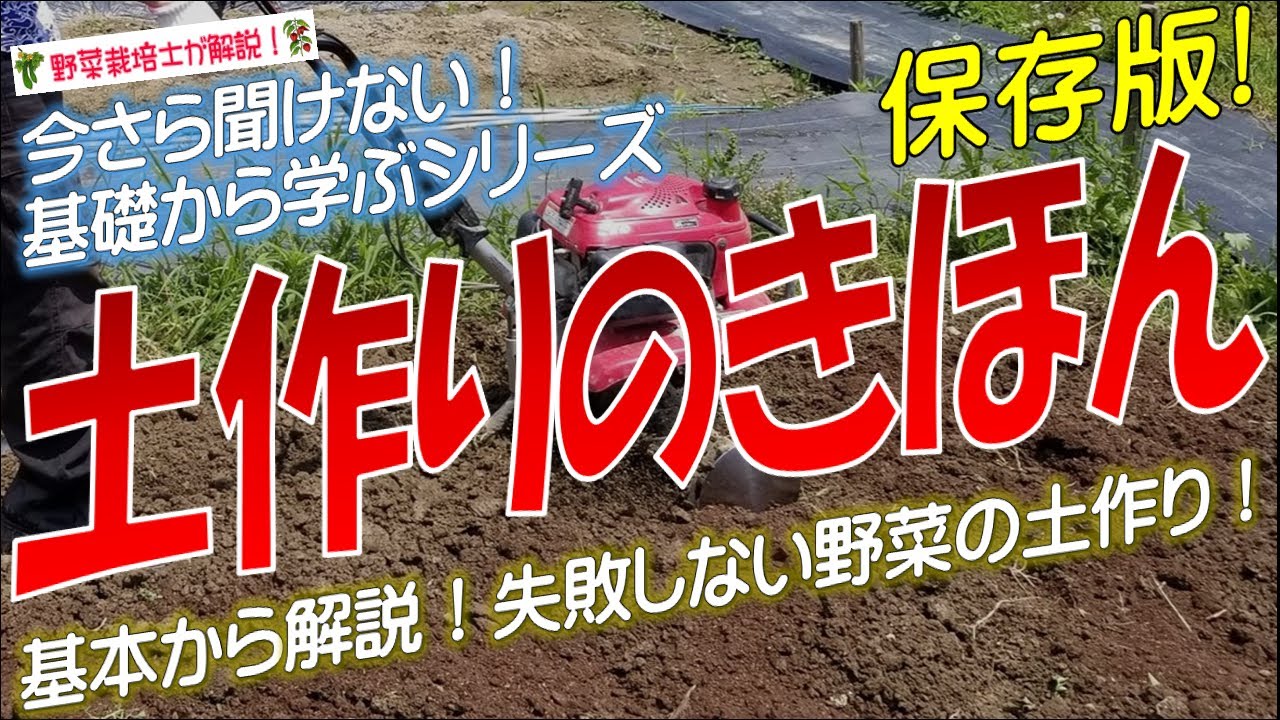
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке:









